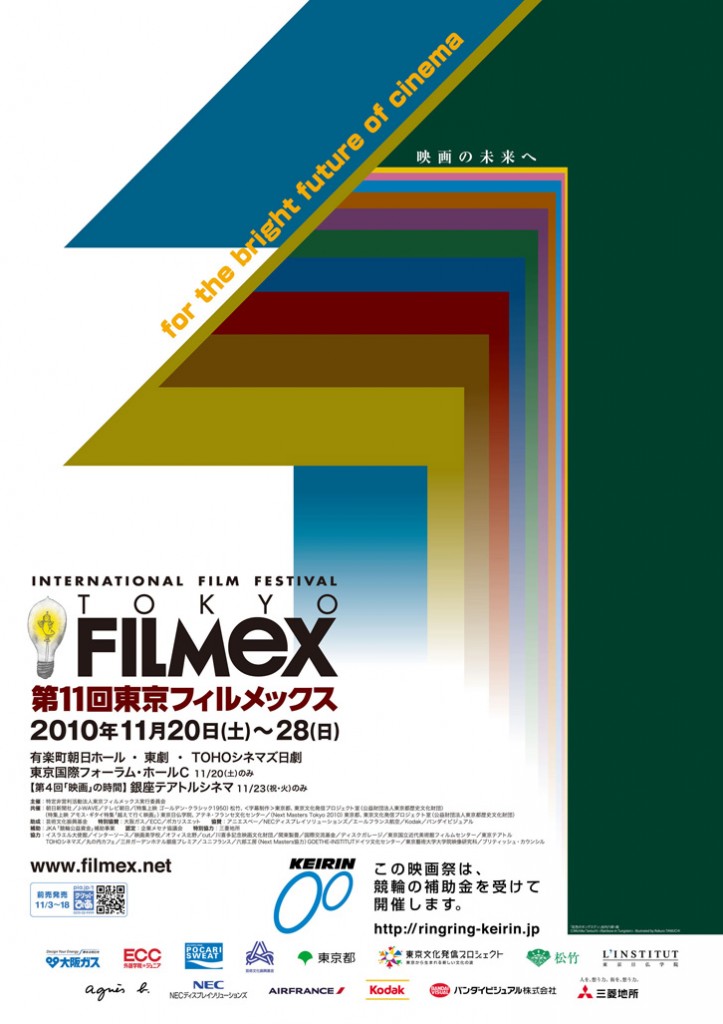彼は闘いのカリスマ。その生き様は伝説。

映画史において30作品以上に渡って映像化されてきた“ロビン・フッド”の伝説を、『グラディエーター』のリドリー・スコット&ラッセル・クロウが装いも新たに復活させた。
『グラディエーター』級の大スペクタクルをメインディッシュに据えながらも、今回最も特徴的なのはそのストーリーだ。これまでのヒーロー伝説とは全く違うアプローチを取り、「なぜ、ロビンフッドは誕生したのか?」「どうして権力に立ち向かおうとしたのか?」といった根本的な部分を見事に再創造した作品に仕上がっている。
そんな本作の日本公開(12月10日)を前に、主演のラッセル・クロウと「LOST」でも知られる共演者ケヴィン・ディランドが来日し、記者会見を行った。ラッセルにとっては『ビューティフル・マインド』以来となる8年ぶり、2度目の来日となる。


以前、『ロビン・フッド』の海外インタビュー中に腹を立てて部屋を飛び出していったことのあるラッセル。等身大の彼もまた、映画のキャラと同じ野生味たっぷりの武勇伝に事欠かない。今回の記者会見も開始時間がだいぶ遅れ、司会者からは「質疑応答は20分ほどになります。フォトセッションは短めになるかもしれません」との事前アナウンスが行われていた。彼の性格上、ということなのだろう。
なにしろ相手は野生味あふれる戦士、グラディエーターなのだ。会見でいったい何が起こるか、どんな奇襲が仕掛けられるのか、我々には見当もつかない。私はゴクリ唾を呑みこみ、会場の記者たちも最低限の覚悟を決めた(多分)。
そして、現場が慌ただしくなる。ついに来た。あいつがやってきた。
ラッセル・クロウ、登場―
そこには予想だにしない笑顔があった。愛想笑いだろうか?いや戦士に偽りは似合わない。あれは満面の笑顔だった。ときに勇ましく顔を引き締め、スーツをパリッと着こなし、ふたりは常に紳士的に振る舞った。そこには野獣の姿は微塵も無かった。
質問が飛ぶ。「あの強靭な肉体を維持すべく、普段からトレーニングされてるんですか?」
ラッセル・クロウ
「今回の映画では6ヶ月間に渡って身体づくりを行ったよ。その主なものはアーチェリーの練習だったけれどね。でもね、映画の予定がないときには全くトレーニングしてないんだ。僕は映画ごとにアプローチを変える。そこでの必要性にあわせて肉体改造もしっかり行うといった感じかな。その過程ではたくさんの生傷に見舞われてきたよ。アキレス腱や脛、腰、肋骨の損傷。それに肩は二度も手術した。年齢を重ねるごとに身体に無理が効かなくなってるのが分かる。それでも素晴らしい作品に仕上げるためなら、多少の傷は仕方ないよ」
なるほど、文字通り肉体をすり減らして映画製作に臨んでいるわけなのか。そんな先輩俳優の姿を間近で目撃してきたデュランドさんは果たして何を感じた?映画の中では粗野なライバルにして最高の仲間となる彼が、物腰柔らかにこう応える。
ケヴィン・デュランド
「彼との共演は今回で3度目だけど、本当にいつも自分の兄貴のようにたくさんのことを学んでる。まず現場での彼は集中力が抜群に高いんだ。なおかつ、みんなで規模の大きなシーンに挑むときには周囲への気配りを忘れない。とても頼りになる存在さ」
また、今回の来日は叶わなかったが、巨匠リドリー・スコットはラッセルについて「長年連れ添った夫婦のような存在」と評しているという。この言葉についてラッセルはこう返した。
ラッセル・クロウ
「長年連れ添った夫婦?ははは、それの意味するところはきっと『完璧』ってことだと思うよ。何をするにしても互いにためらいがない、言葉少なめの『あ・うん』の呼吸で臨める。我々の関係はそんな感じじゃないかな。僕はというと、リドリーを画家のような存在だと思ってる。そして俳優である自分は彼に絵具を渡す役回りだ。彼が『もうちょっと青が欲しい』と言えば、その要求に全力で応えるというわけさ。ルネサンス期の画家に例えるならば、彼はティッチアーノかな。どの作品も非常に精神的、宗教的な主題を感じさせるからね。彼のような稀代のアーティストと仕事ができて本当に嬉しいし、心から感謝しているよ」
その後、日本人ゲストの神田うのさんを招いての束の間のコラボレーション。そして、ついに…ついに懸案のフォトセッションの時間がやってきた。「フォトセッションは短めになるかも」 序盤の注意事項を想いだし、筆者も僅かにみぞおちのあたりが痛くるのを感じたわけだが…
そんな我々が目にしたのは想像を遥かに絶する光景だった。

ラッセル・クロウはおもむろにテレビカメラ陣の方を向き、まさかの笑顔と、ピースサインを決めたのだ。会場にいた全員に衝撃が走った。まさかあのラッセルが!ある者は歓声を上げ、ある者は拍手を送った。会場は最後の一瞬において激しく発火した。もちろん幸福な意味において。
後に確認したラッセルのツイッターでのつぶやきが、また嬉しい。
“Tokyo is awesome.”
“Tokyo premiere tonight. Lighting the Roppongi Hills christmas tree with a sword apparently.Tokyo has been so kind and welcoming. ”
今回の来日によって個人的にラッセル・クロウへの印象が180度変わった。野獣説はマスコミが面白おかしく書きたてているだけだ。実際の彼はとても紳士的で心根の誠実な、最高の戦士だった。




公式HP>http://robinhood-movie.jp/
12月10日(金)、全国ロードショー
配給:東宝東和
【ライター】牛津厚信
.
カテゴリー: 特 集 | 記者会見
2010年11月30日 by p-movie.com